病院指標
令和6年度 熊本セントラル病院 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | – | 15 | 35 | 56 | 117 | 145 | 313 | 595 | 614 | 363 |
【定義】
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
当院を2024.6~2025.5に退院した患者さんの入院時年齢の人数を10歳刻みで集計しています。
【解説】
患者の年齢構成を調べると、その病院の特徴がある程度わかります。年齢層の高い患者が多い病院は若い患者が多い病院より同じ病気でも入院期間が長くなったり、重症化しやすいという傾向があります。
2024年度の総退院患者数は、3.658名ですが、データ対象の一般病棟退院患者は上記となります。70歳以上の入院患者さんが全体の66.4%を占めており、前年と比較しても年齢階級別に大きな変化は見られません。
地域の中核病院、救急輪番病院として他の医療機関とも共同し、地域医療に貢献していきたいと思います。
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
当院を2024.6~2025.5に退院した患者さんの入院時年齢の人数を10歳刻みで集計しています。
【解説】
患者の年齢構成を調べると、その病院の特徴がある程度わかります。年齢層の高い患者が多い病院は若い患者が多い病院より同じ病気でも入院期間が長くなったり、重症化しやすいという傾向があります。
2024年度の総退院患者数は、3.658名ですが、データ対象の一般病棟退院患者は上記となります。70歳以上の入院患者さんが全体の66.4%を占めており、前年と比較しても年齢階級別に大きな変化は見られません。
地域の中核病院、救急輪番病院として他の医療機関とも共同し、地域医療に貢献していきたいと思います。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 63 | 11.89 | 8.88 | 3.17 | 80.67 | 内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP) |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 26 | 4.19 | 2.57 | 0.00 | 65.38 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(前日入院) 内視鏡的大腸ポリープ切除術(当日入院) |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 23 | 18.65 | 16.40 | 13.04 | 89.39 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 20 | 27.65 | 20.78 | 25.00 | 87.30 | |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 18 | 9.78 | 7.60 | 0.00 | 63.89 |
【定義】
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
当院を2024.6~2025.5に退院した患者さんの診療科ごとに症例数の多い上位5つの診断群分類についての集計です。
・DPCコード:病気と治療方法の組み合わせによって分類されますので、同じ病気でも治療方法が違えばDPCコードは異なります。
・DPC名称:病名での分類名称です。
・平均在院日数(自院):該当DPCで入院していた日数の平均値です。
・平均在院日数(全国):厚生労働省より公表されている2024年度における先刻のDPC対象病院の在院日数の平均値です。(外泊日数は除く)
・転院率:退院時、当院から他の病院や診療所に継続して入院(転院)した該当DPCの内の割合です。
【解説】
当院は包括ケア病棟があります。一般病棟で急性期の治療が終了した後、さらに継続的な治療が必要な場合は、包括ケア病棟で行います。そのため、一般病棟だけの病院より当院の平均在院日数は長い傾向にあります。
消化器内科では、肝臓や消化管、胆嚢や膵臓等の消化器疾患に対する検査や治療を行っています。
胆道系疾患は、胆管結石により胆管がつまることで感染を起こし発熱、黄疸を呈し重篤化する可能性があるため、緊急で胆道ドレナージを行います。
大腸ポリープや大腸腺腫など良性腫瘍を切除するポリペクトミー、内視鏡的粘膜切除術(EMR)などの内科的治療が最も多く、EMRは悪性腫瘍に対して行う場合もあります。サイズが大きい場合、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)を行います。
誤嚥性肺炎は、食べ物や唾液を誤嚥し細菌が気管から肺に入ることで起こる肺炎です。嚥下機能が低下した高齢者に多く、繰り返し発症したり、重症化しやすく入院日数も長くなります。抗菌薬を用いた薬物療法が基本となります。
大腸憩室性疾患、下血のみ認める場合と発熱・腹痛を伴う憩室炎があります。
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
当院を2024.6~2025.5に退院した患者さんの診療科ごとに症例数の多い上位5つの診断群分類についての集計です。
・DPCコード:病気と治療方法の組み合わせによって分類されますので、同じ病気でも治療方法が違えばDPCコードは異なります。
・DPC名称:病名での分類名称です。
・平均在院日数(自院):該当DPCで入院していた日数の平均値です。
・平均在院日数(全国):厚生労働省より公表されている2024年度における先刻のDPC対象病院の在院日数の平均値です。(外泊日数は除く)
・転院率:退院時、当院から他の病院や診療所に継続して入院(転院)した該当DPCの内の割合です。
【解説】
当院は包括ケア病棟があります。一般病棟で急性期の治療が終了した後、さらに継続的な治療が必要な場合は、包括ケア病棟で行います。そのため、一般病棟だけの病院より当院の平均在院日数は長い傾向にあります。
消化器内科では、肝臓や消化管、胆嚢や膵臓等の消化器疾患に対する検査や治療を行っています。
胆道系疾患は、胆管結石により胆管がつまることで感染を起こし発熱、黄疸を呈し重篤化する可能性があるため、緊急で胆道ドレナージを行います。
大腸ポリープや大腸腺腫など良性腫瘍を切除するポリペクトミー、内視鏡的粘膜切除術(EMR)などの内科的治療が最も多く、EMRは悪性腫瘍に対して行う場合もあります。サイズが大きい場合、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)を行います。
誤嚥性肺炎は、食べ物や唾液を誤嚥し細菌が気管から肺に入ることで起こる肺炎です。嚥下機能が低下した高齢者に多く、繰り返し発症したり、重症化しやすく入院日数も長くなります。抗菌薬を用いた薬物療法が基本となります。
大腸憩室性疾患、下血のみ認める場合と発熱・腹痛を伴う憩室炎があります。
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130xx9900x0 | 心不全 | 14 | 28.21 | 17.33 | 0.00 | 86.36 | |
| 050070xx99001x | 頻脈性不整脈 | – | – | 13.91 | – | – | |
| 050080xx99001x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | – | – | 18.36 | – | – | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上 | – | – | 16.40 | – | – | |
| 050210xx9900xx | 徐脈性不整脈 | – | – | 7.84 | – | – |
【解説】
循環器内科入院患者では、心不全が最多です。高齢者が多くを占めており、再発も多く、複数の併存疾患をお持ちで、入院前からADL低下を伴う患者が大半です。このため入院早期よりリハビリテーションの介入を行うことで、さらなる廃用の進行を防ぎ、入院前の生活への復帰を目標とし、また回復後には地域の先生方にご紹介させて頂き、地域内の連携で心不全再増悪を予防したいと考えています。
急性心筋梗塞、急性大動脈解離などの当院で実施できない心臓カテーテル検査・治療あるいは手術を要する疾患では、遅滞なく高次医療機関に転送しています。このような疾患では、回復期管理、リハビリテーションで関わっております。
循環器内科入院患者では、心不全が最多です。高齢者が多くを占めており、再発も多く、複数の併存疾患をお持ちで、入院前からADL低下を伴う患者が大半です。このため入院早期よりリハビリテーションの介入を行うことで、さらなる廃用の進行を防ぎ、入院前の生活への復帰を目標とし、また回復後には地域の先生方にご紹介させて頂き、地域内の連携で心不全再増悪を予防したいと考えています。
急性心筋梗塞、急性大動脈解離などの当院で実施できない心臓カテーテル検査・治療あるいは手術を要する疾患では、遅滞なく高次医療機関に転送しています。このような疾患では、回復期管理、リハビリテーションで関わっております。
呼吸器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 18 | 24.61 | 16.40 | 11.11 | 85.22 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 13 | 52.92 | 20.78 | 38.46 | 87.92 | |
| 040110xxxx00xx | 間質性肺炎 | – | – | 18.68 | – | – | |
| 040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | – | – | 22.28 | – | – | |
| 040200xx99x00x | 気胸 | – | – | 9.28 | – | – |
【解説】
呼吸器内科では呼吸器全般の疾患に対応しております。
主な疾患は呼吸器感染症、気管支喘息、呼吸不全、慢性閉塞性肺疾患などです。
急性肺炎に対する抗菌剤治療の他、高齢者に多くみられる誤嚥性肺炎に関しては、言語聴覚士、耳鼻咽喉科医師と相談しながら嚥下機能評価、適切な食事形態の調整などを行います。
慢性閉塞性肺疾患に関しては、全身状態を考慮しながら、気管支拡張剤吸入や呼吸器リハビリテーションを行います。
肺炎のデータに関しては「成人市中肺炎の重症度」もご参照ください。
呼吸器内科では呼吸器全般の疾患に対応しております。
主な疾患は呼吸器感染症、気管支喘息、呼吸不全、慢性閉塞性肺疾患などです。
急性肺炎に対する抗菌剤治療の他、高齢者に多くみられる誤嚥性肺炎に関しては、言語聴覚士、耳鼻咽喉科医師と相談しながら嚥下機能評価、適切な食事形態の調整などを行います。
慢性閉塞性肺疾患に関しては、全身状態を考慮しながら、気管支拡張剤吸入や呼吸器リハビリテーションを行います。
肺炎のデータに関しては「成人市中肺炎の重症度」もご参照ください。
脳神経内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞(エダラボンあり) | 13 | 31.23 | 16.89 | 7.69 | 68.92 | 脳梗塞 HI-UP 脳梗塞(軽症) 脳梗塞(中等症) |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞(リハビリテーションあり) | 10 | 13.40 | 16.94 | 30.00 | 75.00 | 脳梗塞 HI-UP 脳梗塞(軽症) 脳梗塞(中等症) |
| 010060xx99x41x | 脳梗塞(エダラボンあり・副傷病あり) | – | – | 29.66 | – | – | 脳梗塞 HI-UP 脳梗塞(軽症) 脳梗塞(中等症) |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | – | – | 20.78 | – | – | |
| 010160xx99x00x | パーキンソン病 | – | – | 17.95 | – | – |
【解説】
脳神経内科では、脳・脊髄などの神経および筋肉の疾患の専門外来診療を行なっております。脳梗塞、頭痛、てんかん、認知症、顔面神経麻痺、パーキンソン病、髄膜炎、重症筋無力症、脊髄小脳変性症、ギラン・バレー症候群などの疾患に対応しています。
地域包括ケア病棟での入院症例は上記に含まれていないため、実際には当科で入院されていた患者様は、2024.6~2025.5の1年間で合計122名、うち脳梗塞が50名、パーキンソン病およびパーキンソン症候群が22名、認知症が13名でした。
頭痛やけいれん、意識消失、身体の動作や感覚の異常などを自覚された場合は当科にご相談ください。なお診断が確定し、治療で症状が安定した場合は、当科からかかりつけの病院へ転院を推奨しております。
脳神経内科では、脳・脊髄などの神経および筋肉の疾患の専門外来診療を行なっております。脳梗塞、頭痛、てんかん、認知症、顔面神経麻痺、パーキンソン病、髄膜炎、重症筋無力症、脊髄小脳変性症、ギラン・バレー症候群などの疾患に対応しています。
地域包括ケア病棟での入院症例は上記に含まれていないため、実際には当科で入院されていた患者様は、2024.6~2025.5の1年間で合計122名、うち脳梗塞が50名、パーキンソン病およびパーキンソン症候群が22名、認知症が13名でした。
頭痛やけいれん、意識消失、身体の動作や感覚の異常などを自覚された場合は当科にご相談ください。なお診断が確定し、治療で症状が安定した場合は、当科からかかりつけの病院へ転院を推奨しております。
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 58 | 6.38 | 4.54 | 0.00 | 73.28 | 腹腔鏡下鼡径ヘルニア根治術 |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 | 41 | 7.22 | 7.05 | 4.88 | 60.17 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 22 | 6.00 | 5.99 | 0.00 | 53.82 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 18 | 5.72 | 5.32 | 0.00 | 44.56 | 腹腔鏡下虫垂切除術(穿孔・膿瘍なし)-虫垂炎 |
| 060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 | 15 | 18.00 | 14.81 | 0.00 | 75.73 | S状結腸切除・直腸切除 結腸切除 |
【解説】
外科では、鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下または鼠径部切開による鼠径ヘルニア手術症例が多くなっています。胆嚢炎や胆石症に対する手術症例は、ほとんどを腹腔鏡下手術で行っております。虫垂周囲膿瘍を伴わない虫垂炎は、20代~40代の比較的若い世代が多くなっています。
結腸癌の症例数は年々増加傾向で、腹腔鏡下手術が増えています。また、各種固形がんの初発・再発症例、化学療法、手術不能例に対する温熱療法(ハイパーサーミア)治療にも対応しています。
外科では、鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下または鼠径部切開による鼠径ヘルニア手術症例が多くなっています。胆嚢炎や胆石症に対する手術症例は、ほとんどを腹腔鏡下手術で行っております。虫垂周囲膿瘍を伴わない虫垂炎は、20代~40代の比較的若い世代が多くなっています。
結腸癌の症例数は年々増加傾向で、腹腔鏡下手術が増えています。また、各種固形がんの初発・再発症例、化学療法、手術不能例に対する温熱療法(ハイパーサーミア)治療にも対応しています。
血管外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 | 33 | 2.27 | 2.66 | 0.00 | 67.12 | 下肢静脈瘤除去手術 両下肢静脈瘤除去手術 |
| 050170xx03001x | 閉塞性動脈疾患 | – | – | 9.29 | – | – | |
【解説】
静脈・リンパ節疾患は、血管外科で最も多い症例になります。深部静脈血栓症か下肢静脈瘤の治療が主になります。下肢静脈瘤に対する血管内塞栓術は、2024年度22症例行っています。
また、整形外科との連携により下肢手術の術前術後にエコーを行い、深部静脈血栓の予防、治療に努めています。
静脈・リンパ節疾患は、血管外科で最も多い症例になります。深部静脈血栓症か下肢静脈瘤の治療が主になります。下肢静脈瘤に対する血管内塞栓術は、2024年度22症例行っています。
また、整形外科との連携により下肢手術の術前術後にエコーを行い、深部静脈血栓の予防、治療に努めています。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 134 | 46.10 | 25.29 | 41.04 | 86.48 | 大腿骨骨折(骨接合術) 大腿骨骨折(人工骨頭置換術) |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 106 | 35.33 | 21.38 | 0.94 | 75.87 | 人工膝関節置換術(TKA) |
| 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)手術あり(椎弓形成、椎弓切除) | 101 | 19.95 | 15.41 | 0.99 | 74.90 | 腰椎除圧・固定・椎弓形成 硬膜外腔癒着剥離術(TSCP) |
| 070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)手術あり(後方椎体固定、前方後方同時固定、後方又は後側方固定) | 94 | 21.87 | 19.60 | 0.00 | 72.37 | |
| 070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)手術なし(脳脊髄腔造影剤使用撮影あり) | 78 | 2.00 | 2.56 | 0.00 | 74.33 | ミエロ(腰椎・頸椎) |
【解説】
整形外科では大腿骨の骨折(股関節・大腿近位の骨折)での入院が最も多くなっています。変形性膝関節症に関しては、本人の歩行状態の改善までしっかりリハビリを行っておりますので、入院が少し長くなっています。変形性股関節症に対しても低侵襲な治療を目指し、筋肉を切離しない前方アプローチによる人工股関節置換術を行っております。
2021年から脊椎疾患に対する手術加療を開始、腫瘍性病変以外のすべての脊椎疾患対して加療を行っております。
特に当院においては、2023年度からO-arm+ナビゲーションシステムを用いた治療を開始、固定を要する手術に活用しております。また同システムを用いて、前方後方同時固定(OLIF)を多く行い、低侵襲で手術を行うことにより、より早期の退院に貢献しております。
整形外科では大腿骨の骨折(股関節・大腿近位の骨折)での入院が最も多くなっています。変形性膝関節症に関しては、本人の歩行状態の改善までしっかりリハビリを行っておりますので、入院が少し長くなっています。変形性股関節症に対しても低侵襲な治療を目指し、筋肉を切離しない前方アプローチによる人工股関節置換術を行っております。
2021年から脊椎疾患に対する手術加療を開始、腫瘍性病変以外のすべての脊椎疾患対して加療を行っております。
特に当院においては、2023年度からO-arm+ナビゲーションシステムを用いた治療を開始、固定を要する手術に活用しております。また同システムを用いて、前方後方同時固定(OLIF)を多く行い、低侵襲で手術を行うことにより、より早期の退院に貢献しております。
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030428xxxxx1xx | 突発性難聴(高気圧酸素療法あり) | 18 | 9.28 | 9.42 | 0.00 | 60.22 | 突発性難聴 |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | – | – | 5.63 | – | – | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | – | – | 4.67 | – | – | |
| 030428xxxxx0xx | 突発性難聴(手術・処置なし) | – | – | 8.21 | – | – | |
【解説】
耳鼻咽喉科で最も多い症例は突発性難聴で、高気圧酸素治療やステロイドの点滴などを行います。高気圧酸素治療は、装置の中に入り、大気圧より高い気圧環境の中で酸素を吸入することにより病態の改善を図る治療です。
扁桃周囲膿瘍は、放置すると危険な病気です。近医より紹介を頂き切開などの処置を行っています。
メニエール病や良性発作性めまい症などの急なめまいによる入院も対応しています。当院耳鼻咽喉科では、入院を要する急性期の疾患に可能な限り対応するようにしています。
睡眠時無呼吸症候群に対する1泊検査入院もしています。
地域包括ケア病棟での入院症例は上記に含まれていない為、実際には2024年度157例の入院に対応しており、口蓋扁桃摘出手術や副鼻腔炎手術、声帯ポリープ手術、唾石症手術等も行っております。
耳鼻咽喉科で最も多い症例は突発性難聴で、高気圧酸素治療やステロイドの点滴などを行います。高気圧酸素治療は、装置の中に入り、大気圧より高い気圧環境の中で酸素を吸入することにより病態の改善を図る治療です。
扁桃周囲膿瘍は、放置すると危険な病気です。近医より紹介を頂き切開などの処置を行っています。
メニエール病や良性発作性めまい症などの急なめまいによる入院も対応しています。当院耳鼻咽喉科では、入院を要する急性期の疾患に可能な限り対応するようにしています。
睡眠時無呼吸症候群に対する1泊検査入院もしています。
地域包括ケア病棟での入院症例は上記に含まれていない為、実際には2024年度157例の入院に対応しており、口蓋扁桃摘出手術や副鼻腔炎手術、声帯ポリープ手術、唾石症手術等も行っております。
総合診療科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 43 | 19.88 | 16.40 | 13.95 | 88.23 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 15 | 30.27 | 13.66 | 6.67 | 86.93 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 13 | 31.33 | 20.78 | 30.77 | 83.00 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 | – | – | 17.33 | – | – | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | – | – | 5.55 | – | – |
【解説】
様々な症状に対して臓器別専門医と連携し、全身状態をみながら治療をおこなっています。その為、疾患も肺炎、感染症、心不全と多岐に渡っています。
様々な症状に対して臓器別専門医と連携し、全身状態をみながら治療をおこなっています。その為、疾患も肺炎、感染症、心不全と多岐に渡っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 14 | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 12 | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 肝癌 | – | – | – | – | – | 18 | 1 | 8 |
【定義】
10症例以下は表示させていません。
日本でもっとも罹患率の高い5大がんの病期(stage)症例数を集計したものです。病期(stage)とは、がんの進行状況を示します。
UICC TNM病期分類にて原発巣がんのstage(Ⅰ期~Ⅳ期)を決定しています。
Ⅰ期に近い程、がんが小さくとどまっている状態で、Ⅳ期に近い程、がんが広がっている状態です。
Ⅰ期の患者が多ければ早期にがんを発見しており、Ⅳ期の症例が多いほど重症の患者が多い事がわかります。また、stage(病期)により治療方針が変わります。
【解説】
当院では急性期病院との連携をとり治療を行っています。各種固形がんの再発症例、手術不能例に対しても、化学療法、ハイパーサーミア、高気圧酸素療法を組み合わせた集学的治療を運用し地域医療に貢献しています。特に肝がんは再発することが多い病気であり、当院でも再発治療を多く扱っています。
肝切除、ラジオ波凝固療法、肝動脈塞栓、動注療法について、最新の治療に対応しています。
10症例以下は表示させていません。
日本でもっとも罹患率の高い5大がんの病期(stage)症例数を集計したものです。病期(stage)とは、がんの進行状況を示します。
UICC TNM病期分類にて原発巣がんのstage(Ⅰ期~Ⅳ期)を決定しています。
Ⅰ期に近い程、がんが小さくとどまっている状態で、Ⅳ期に近い程、がんが広がっている状態です。
Ⅰ期の患者が多ければ早期にがんを発見しており、Ⅳ期の症例が多いほど重症の患者が多い事がわかります。また、stage(病期)により治療方針が変わります。
【解説】
当院では急性期病院との連携をとり治療を行っています。各種固形がんの再発症例、手術不能例に対しても、化学療法、ハイパーサーミア、高気圧酸素療法を組み合わせた集学的治療を運用し地域医療に貢献しています。特に肝がんは再発することが多い病気であり、当院でも再発治療を多く扱っています。
肝切除、ラジオ波凝固療法、肝動脈塞栓、動注療法について、最新の治療に対応しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 14 | 8.93 | 49.50 |
| 中等症 | 77 | 17.21 | 83.38 |
| 重症 | 22 | 24.18 | 89.32 |
| 超重症 | 11 | 21.18 | 83.09 |
| 不明 | – | – | – |
【定義】
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
当院を2024.6~2025.5に退院した患者で、成人市中肺炎の重症別患者数を集計したものです。成人とは15歳以上の患者です。市中肺炎とは普段の生活の中で罹患した肺炎を指します。入院契機傷病名および最も医療資源を投入した傷病名のICD10コードがJ13~J18であるものが対象です。そのため、インフルエンザウイルスからの肺炎、誤嚥性肺炎等は集計対象外になります。
・平均在院日数:該当DPCで当院に入院していた日数の平均値です。
重症度は、市中肺炎ガイドラインのよる重症度分類(A-DROP)システムにより分類しています。
【A-DROP】
A(Age):男性70歳以上、女性75歳以上
D(Dehydration):BUN21mg/dl以上または脱水
R(Respiration):SpO2 90%以下(PaO2 60torr以下)
O(Orientation):意識障害あり
P(Pressure):血圧(収縮期)90mmHg以下
軽 度:(重症度0)上記の指標のいずれも満たさないもの
中程度:(重症度1・2)1~2項目に該当するもの
重 症:(重症度3)3項目該当するもの
超重症:(重症度4・5)4項目以上に該当するもの。ただし、ショックがあれば1項目のみでも超重症とする。
【解説】
10症例未満は表示させていません。
中等度の平均年齢は83歳、重症の平均年齢は89歳と高齢になっています。中等度の患者数が最も多く、市中肺炎全体の62%です。重症度が上がると、治療期間も長くなる傾向があり、長期臥床による筋力・体力低下を防ぐために、可能な限り理学療法(リハビリ)を併用しています。成人市中肺炎のガイドラインでは、軽症の患者さんは外来治療でよいことになっていますが、併存に喘息やがん、先天性の疾患があるなど重症化することを考慮し入院となっている場合があります。
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
当院を2024.6~2025.5に退院した患者で、成人市中肺炎の重症別患者数を集計したものです。成人とは15歳以上の患者です。市中肺炎とは普段の生活の中で罹患した肺炎を指します。入院契機傷病名および最も医療資源を投入した傷病名のICD10コードがJ13~J18であるものが対象です。そのため、インフルエンザウイルスからの肺炎、誤嚥性肺炎等は集計対象外になります。
・平均在院日数:該当DPCで当院に入院していた日数の平均値です。
重症度は、市中肺炎ガイドラインのよる重症度分類(A-DROP)システムにより分類しています。
【A-DROP】
A(Age):男性70歳以上、女性75歳以上
D(Dehydration):BUN21mg/dl以上または脱水
R(Respiration):SpO2 90%以下(PaO2 60torr以下)
O(Orientation):意識障害あり
P(Pressure):血圧(収縮期)90mmHg以下
軽 度:(重症度0)上記の指標のいずれも満たさないもの
中程度:(重症度1・2)1~2項目に該当するもの
重 症:(重症度3)3項目該当するもの
超重症:(重症度4・5)4項目以上に該当するもの。ただし、ショックがあれば1項目のみでも超重症とする。
【解説】
10症例未満は表示させていません。
中等度の平均年齢は83歳、重症の平均年齢は89歳と高齢になっています。中等度の患者数が最も多く、市中肺炎全体の62%です。重症度が上がると、治療期間も長くなる傾向があり、長期臥床による筋力・体力低下を防ぐために、可能な限り理学療法(リハビリ)を併用しています。成人市中肺炎のガイドラインでは、軽症の患者さんは外来治療でよいことになっていますが、併存に喘息やがん、先天性の疾患があるなど重症化することを考慮し入院となっている場合があります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 30 | 34.23 | 73.10 | 26.32 |
| その他 | – | – | – | – |
【定義】
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
当院を2024.6~2025.5に退院した患者で、脳梗塞について集計したものです。
・平均在院日数:該当DPCで当院に入院していた日数の平均値です。
・転院率:退院時当院から他の病院や診療所に継続して入院(転院)した該当DPCの内の割合です
【解説】
当院では急性期治療からリハビリまでを一貫しておこなっているため、入院日数は比較的長くなっています。
尚、最新の血管内治療(血栓回収療法)等が必要な症例は高次機能病院に御紹介しています。
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
当院を2024.6~2025.5に退院した患者で、脳梗塞について集計したものです。
・平均在院日数:該当DPCで当院に入院していた日数の平均値です。
・転院率:退院時当院から他の病院や診療所に継続して入院(転院)した該当DPCの内の割合です
【解説】
当院では急性期治療からリハビリまでを一貫しておこなっているため、入院日数は比較的長くなっています。
尚、最新の血管内治療(血栓回収療法)等が必要な症例は高次機能病院に御紹介しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 58 | 3.62 | 10.78 | 1.72 | 82.12 | 内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP) |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 27 | 1.85 | 2.22 | 3.70 | 62.11 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(前日入院) 内視鏡的大腸ポリープ切除術(当日入院) |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 20 | 0.20 | 11.15 | 10.00 | 72.20 | |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 13 | 0.92 | 9.85 | 30.77 | 69.62 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 11 | 0.91 | 10.55 | 0.00 | 77.91 | 胃内視鏡的粘膜切除術(ESD) |
【定義】
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
当院を2024.6~2025.5に退院した患者さんの診療科ごとに手術症例数の多い上位5つの診断群分類についての集計です。診療科は医療資源を最も投入した傷病の診察担当医師の所属する科とし、複数の診療科では重複してカウントしていません。
・Kコード:手術術式の点数表コードです。
・名称:手術術式の名称です。
・平均術前日数:入院日から手術日前日まで(手術日当日は含まない)の平均日数です。
・平均術後日数:手術日翌日(手術日当日は含まない)から退院日までの平均日数です。
・転院率:退院時当院から他の病院や診療所に継続して入院(転院)した該当DPCの内の割合です。
【解説】
消化器内科では、胆管炎や胆管癌による閉塞性黄疸に対して行う内視鏡的ステント留置術や乳頭切開を行い出口を拡げて石を出やすくする手術も上位を占めます。
大腸の腺腫や早期癌の患者さんに対して施行する内視鏡的大腸ポリープ粘膜切除術が病院全体では最も多く、病変が早期の段階での治療に努めています。
予定入院のため、手術までの日数も短い状態です。
内視鏡的消化管止血術は、胃・十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、マロリーワイス症候群からの出血などに対し、クリップ止血法、エタノール等の局注法、熱凝固法などを行います。大量出血があると出血性ショックや貧血状態になったりしますので、緊急対応が必要となります。また、出血を止めるだけではなく、原因となる病態の治療も行うため治療期間は患者によりばらつきがあります。
内視鏡により、早期の食道癌、胃癌、大腸癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)も行っています。
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
当院を2024.6~2025.5に退院した患者さんの診療科ごとに手術症例数の多い上位5つの診断群分類についての集計です。診療科は医療資源を最も投入した傷病の診察担当医師の所属する科とし、複数の診療科では重複してカウントしていません。
・Kコード:手術術式の点数表コードです。
・名称:手術術式の名称です。
・平均術前日数:入院日から手術日前日まで(手術日当日は含まない)の平均日数です。
・平均術後日数:手術日翌日(手術日当日は含まない)から退院日までの平均日数です。
・転院率:退院時当院から他の病院や診療所に継続して入院(転院)した該当DPCの内の割合です。
【解説】
消化器内科では、胆管炎や胆管癌による閉塞性黄疸に対して行う内視鏡的ステント留置術や乳頭切開を行い出口を拡げて石を出やすくする手術も上位を占めます。
大腸の腺腫や早期癌の患者さんに対して施行する内視鏡的大腸ポリープ粘膜切除術が病院全体では最も多く、病変が早期の段階での治療に努めています。
予定入院のため、手術までの日数も短い状態です。
内視鏡的消化管止血術は、胃・十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、マロリーワイス症候群からの出血などに対し、クリップ止血法、エタノール等の局注法、熱凝固法などを行います。大量出血があると出血性ショックや貧血状態になったりしますので、緊急対応が必要となります。また、出血を止めるだけではなく、原因となる病態の治療も行うため治療期間は患者によりばらつきがあります。
内視鏡により、早期の食道癌、胃癌、大腸癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)も行っています。
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 69 | 1.06 | 5.16 | 2.90 | 59.81 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 31 | 1.00 | 4.61 | 0.00 | 75.97 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 27 | 1.00 | 4.11 | 0.00 | 70.19 | 腹腔鏡下鼡径ヘルニア根治術 |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 19 | 0.26 | 5.32 | 0.00 | 46.79 | 腹腔鏡下虫垂切除術(穿孔・膿瘍なし)-虫垂炎 |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 14 | 2.71 | 14.71 | 0.00 | 75.43 | S状結腸切除・直腸切除 結腸切除 |
【解説】
外科では、消化器領域の多様な疾患に広く対応しており、腹腔鏡下手術を多く行っています。腹腔鏡下手術は、開腹手術に比べ創が小さいため患者さんの体の負担も少なく回復も早いため、件数も年々増加し外科の全手術の70.2%を占めています。
鼠径ヘルニア手術および腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術は、お腹の壁にできてしまった脆弱部(ヘルニア門)をメッシュ(人工膜)で覆い補強する手術が主流です。
腹腔鏡下虫垂切除術は、緊急手術となる場合が多く、1日未満の術前日数となっています。
胃がん、大腸がん、肝がんなどに対する腹腔鏡下手術から、転移再発がんに対する拡大手術、化学療法、手術不能例に対する温熱療法(ハイパーサーミア)治療までがんの進行に応じた治療をおこなっています。
外科では、消化器領域の多様な疾患に広く対応しており、腹腔鏡下手術を多く行っています。腹腔鏡下手術は、開腹手術に比べ創が小さいため患者さんの体の負担も少なく回復も早いため、件数も年々増加し外科の全手術の70.2%を占めています。
鼠径ヘルニア手術および腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術は、お腹の壁にできてしまった脆弱部(ヘルニア門)をメッシュ(人工膜)で覆い補強する手術が主流です。
腹腔鏡下虫垂切除術は、緊急手術となる場合が多く、1日未満の術前日数となっています。
胃がん、大腸がん、肝がんなどに対する腹腔鏡下手術から、転移再発がんに対する拡大手術、化学療法、手術不能例に対する温熱療法(ハイパーサーミア)治療までがんの進行に応じた治療をおこなっています。
血管外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K617-6 | 下肢静脈瘤血管内塞栓術 | 18 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 68.44 | 両下肢静脈瘤除去手術 下肢静脈瘤除去手術 |
| K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 14 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 64.86 | 両下肢静脈瘤除去手術 下肢静脈瘤除去手術 |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – | |
【解説】
血管外科では、下肢の静脈瘤に対する下肢静脈瘤血管内塞栓術の症例数が最も多くなっています。
今までは下肢静脈瘤血管内焼灼術が中心でしたが、接着剤による治療(下肢静脈瘤血管内塞栓術)が増えてきています。下肢静脈瘤血管内焼灼術よりもさらに低侵襲な治療法です。
静脈瘤に薬を注射して固めてしまう硬化療法や焼灼術、塞栓術が適応とならない方には、静脈を切除するストリッピング手術も行っています。
血管外科では、下肢の静脈瘤に対する下肢静脈瘤血管内塞栓術の症例数が最も多くなっています。
今までは下肢静脈瘤血管内焼灼術が中心でしたが、接着剤による治療(下肢静脈瘤血管内塞栓術)が増えてきています。下肢静脈瘤血管内焼灼術よりもさらに低侵襲な治療法です。
静脈瘤に薬を注射して固めてしまう硬化療法や焼灼術、塞栓術が適応とならない方には、静脈を切除するストリッピング手術も行っています。
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術(肩・股・膝) | 156 | 1.26 | 31.79 | 0.64 | 74.99 | 人工股関節置換術(THA) 人工膝関節置換術(TKA) |
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 115 | 1.87 | 21.70 | 4.35 | 73.08 | 腰椎除圧・固定・椎弓形成 |
| K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨・上腕・大腿) | 104 | 6.71 | 37.60 | 39.42 | 86.63 | 大腿骨骨折(骨接合術) |
| K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 50 | 1.24 | 20.46 | 0.00 | 72.98 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(肩・股) | 47 | 7.47 | 39.40 | 38.30 | 85.23 | 人工骨頭 |
【解説】
整形外科では、人工関節置換術が最も多く、そのうち膝関節に対するものが119症例となっています。手術後は、リハビリ加療を行い退院となります。
手術前後は血管外科による深部静脈血栓症の評価をおこなっています。
骨を金属などで固定する骨折観血的手術が294症例あります。高齢の救急入院患者が多く、入院後に手術前のコントロール(血糖やお薬)を行うため、平均術前日数は長くなっています。
人工骨頭挿入術は、大腿骨頚部骨折や大腿骨骨頭壊死などで行われます。観血的手術と同様平均年齢も高く、術前日数も7.47日、術後日数も39.40日で歩行能力の再獲得まで時間を要します。
脊椎においては、腰部脊柱管狭窄症に対しての椎弓形成術が最も多く行われております。当院では、脊椎手術において最先端のO-arm+ナビゲーションシステムを熊本県で初めて導入いたしました。O-armを用いることにより、高精細画像を取得でき、2Dだけでなく3D画像を手術中にリアルタイムにて確認することができ、より正確で安全な手術をサポートします。また、頻繁にX線透視を行わない為、患者、術者、スタッフのX線被ばく量の軽減に大きく貢献します。
整形外科では、人工関節置換術が最も多く、そのうち膝関節に対するものが119症例となっています。手術後は、リハビリ加療を行い退院となります。
手術前後は血管外科による深部静脈血栓症の評価をおこなっています。
骨を金属などで固定する骨折観血的手術が294症例あります。高齢の救急入院患者が多く、入院後に手術前のコントロール(血糖やお薬)を行うため、平均術前日数は長くなっています。
人工骨頭挿入術は、大腿骨頚部骨折や大腿骨骨頭壊死などで行われます。観血的手術と同様平均年齢も高く、術前日数も7.47日、術後日数も39.40日で歩行能力の再獲得まで時間を要します。
脊椎においては、腰部脊柱管狭窄症に対しての椎弓形成術が最も多く行われております。当院では、脊椎手術において最先端のO-arm+ナビゲーションシステムを熊本県で初めて導入いたしました。O-armを用いることにより、高精細画像を取得でき、2Dだけでなく3D画像を手術中にリアルタイムにて確認することができ、より正確で安全な手術をサポートします。また、頻繁にX線透視を行わない為、患者、術者、スタッフのX線被ばく量の軽減に大きく貢献します。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – |
【定義】
播種性血管内凝固症候群、敗血症、真菌症、手術・処置等の合併症の患者数と発生率です。
・DPC:6桁のDPCコードでの集計です。6桁は病名による分類のみで治療法は関係しません。
・入院契機:入院の契機になった病気です。「同一」か「異なる」とは、請求の対象となる主に治療した病名と入院契機病名との比較です。
「同一」はその病気の治療目的で入院し主にその病気の治療を主に行ったという事です。
「異なる」は別の病気の治療目的で入院し、併発や入院後発症した病気の治療(ここでは播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症、
手術・処置後の合併症)を主に行ったという事です。
・発生率:全退院患者さんのうち該当するDPCの請求となった患者さんの割合です。そのため、実際の発生件数とは異なります
・播種性血管内凝固:感染症などによって起こる、全身性の重症な病態です。
・敗血症:細菌が全身に回り、炎症を起こす重症な病態です。
・真菌症:真菌による感染症です。
・手術・処置後の合併症:手術や処置などに一定割合で発生する病態です。
【解説】
10症例未満のため表示させていません。
播種性血管内凝固症候群、敗血症、真菌症、手術・処置等の合併症の患者数と発生率です。
・DPC:6桁のDPCコードでの集計です。6桁は病名による分類のみで治療法は関係しません。
・入院契機:入院の契機になった病気です。「同一」か「異なる」とは、請求の対象となる主に治療した病名と入院契機病名との比較です。
「同一」はその病気の治療目的で入院し主にその病気の治療を主に行ったという事です。
「異なる」は別の病気の治療目的で入院し、併発や入院後発症した病気の治療(ここでは播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症、
手術・処置後の合併症)を主に行ったという事です。
・発生率:全退院患者さんのうち該当するDPCの請求となった患者さんの割合です。そのため、実際の発生件数とは異なります
・播種性血管内凝固:感染症などによって起こる、全身性の重症な病態です。
・敗血症:細菌が全身に回り、炎症を起こす重症な病態です。
・真菌症:真菌による感染症です。
・手術・処置後の合併症:手術や処置などに一定割合で発生する病態です。
【解説】
10症例未満のため表示させていません。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 700 | 587 | 83.86 |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 623 | 532 | 85.39 |
【定義】
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
分母:血液培養オーダー日数
分子:血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数
【解説】
当院では発熱や細菌感染が疑われる場合、血液培養2セット採取を基本としています。
多職種で構成された抗菌薬適正使用支援チームが主治医と連携して感染症治療の支援、検査の提案等を行っています。
昨年度の血液培養実施率は全国平均を上回った水準で維持しています。
今後も抗菌薬の適正使用を推進していきます。
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
分母:血液培養オーダー日数
分子:血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数
【解説】
当院では発熱や細菌感染が疑われる場合、血液培養2セット採取を基本としています。
多職種で構成された抗菌薬適正使用支援チームが主治医と連携して感染症治療の支援、検査の提案等を行っています。
昨年度の血液培養実施率は全国平均を上回った水準で維持しています。
今後も抗菌薬の適正使用を推進していきます。
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 168 | 139 | 82.74 |
【定義】
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
分母:広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数
分子:分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数
【解説】
不適切な抗菌薬の使用は、耐性菌の発生や蔓延の原因になることから、各医療機関において抗菌薬適正使用支援チーム(Antimicrobial Stewardship Team:AST)を組織するなど、抗菌薬適正使用を推進する取り組みが求められます。抗菌薬適正使用の鍵を握るのは正確な微生物学的診断であり、抗菌薬投与前の適切な検体採取と培養検査が必要です。
当院では、指定抗菌薬(抗MRSA薬、カルバペネム系薬、キノロン系薬等)を届出制とし広域抗菌薬使用患者の全例把握を行っています。また、血液培養陽性患者においてはASTにて介入を行い抗菌薬適正使用に努めています。
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
分母:広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数
分子:分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数
【解説】
不適切な抗菌薬の使用は、耐性菌の発生や蔓延の原因になることから、各医療機関において抗菌薬適正使用支援チーム(Antimicrobial Stewardship Team:AST)を組織するなど、抗菌薬適正使用を推進する取り組みが求められます。抗菌薬適正使用の鍵を握るのは正確な微生物学的診断であり、抗菌薬投与前の適切な検体採取と培養検査が必要です。
当院では、指定抗菌薬(抗MRSA薬、カルバペネム系薬、キノロン系薬等)を届出制とし広域抗菌薬使用患者の全例把握を行っています。また、血液培養陽性患者においてはASTにて介入を行い抗菌薬適正使用に努めています。
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 44609 | 155 | 3.47 |
【定義】
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
分母:退院患者の在院日数の総和
分子:退院患者に発生した転倒・転落件数
計算した値に×1000
【解説】
当院では、入院時・転棟時に転倒・転落アセスメントスコアにて「危険度Ⅲ」の患者に対しては、多職種で危険予知評価を行い患者に応じた環境設定を行っています。97.7%と非常に高い実施率です。
「転倒・転落防止チーム」を発足しており、毎月転倒・転落についてデータをグラフ化し、チームで要因分析を行っています。
また、転倒患者のベッド周囲のラウンドを2~3例/月実施し、結果を各部署へフィードバックしています。
転倒患者の転倒後のカンファレンスも多職種で行い実施率も96.8%と高く、繰り返し転倒することのないように努めています。
今後も、多職種で転倒・転落防止に努めていきたいと思います。
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
分母:退院患者の在院日数の総和
分子:退院患者に発生した転倒・転落件数
計算した値に×1000
【解説】
当院では、入院時・転棟時に転倒・転落アセスメントスコアにて「危険度Ⅲ」の患者に対しては、多職種で危険予知評価を行い患者に応じた環境設定を行っています。97.7%と非常に高い実施率です。
「転倒・転落防止チーム」を発足しており、毎月転倒・転落についてデータをグラフ化し、チームで要因分析を行っています。
また、転倒患者のベッド周囲のラウンドを2~3例/月実施し、結果を各部署へフィードバックしています。
転倒患者の転倒後のカンファレンスも多職種で行い実施率も96.8%と高く、繰り返し転倒することのないように努めています。
今後も、多職種で転倒・転落防止に努めていきたいと思います。
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| 44609 | 7 | 0.16 |
【定義】
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
分母:退院患者の在院日数の総和
分子:退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生件数
計算した値に×1000
【解説】
当院では、緩衝マットやころやわマットを積極的に使用し、「転倒しても骨折しない環境作り」を行っています。
この7件の内4件が、トイレ又はポータブルトイレでの排泄後の転倒によるものです。
ベッドサイドだけでなく、トイレやロビー、浴室など転倒の危険性のある場所での「転倒しない・転倒しても骨折しない」環境設定を行い、3b以上の発生率の低減に努めていきます。
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
分母:退院患者の在院日数の総和
分子:退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生件数
計算した値に×1000
【解説】
当院では、緩衝マットやころやわマットを積極的に使用し、「転倒しても骨折しない環境作り」を行っています。
この7件の内4件が、トイレ又はポータブルトイレでの排泄後の転倒によるものです。
ベッドサイドだけでなく、トイレやロビー、浴室など転倒の危険性のある場所での「転倒しない・転倒しても骨折しない」環境設定を行い、3b以上の発生率の低減に努めていきます。
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルをダウンロード
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 814 | 814 | 100 |
【定義】
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
分母:全身麻酔手術で、予防的抗菌薬が実施された手術件数
分子:分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数
【解説】
手術部位感染(SSI: Surgical Site Infection)は、周術期の重大な合併症の一つです。SSIは入院期間の延長、医療費の増加、予後の悪化を引き起こすため、予防的抗菌薬投与(SAP: Surgical Antimicrobial Prophylaxis)による感染予防が非常に重要です。その中でも、「適切なタイミングでの投与」は、最も重要な因子の一つとされています。
○術前1時間以内の投与の科学的根拠
予防的抗菌薬の効果を最大限に発揮させるには、手術開始時に十分な組織内抗菌薬濃度が必要です。抗菌薬の血中・組織移行動態を考慮すると、点滴投与開始から組織移行・定常状態に達するのにおおよそ30〜60分かかるとされます。よって、手術開始の60分以内に投与を完了することが推奨されています。また、日本化学療法学会/日本外科感染症学会「外科領域における抗菌薬適正使用のガイドライン2020」においても「術開始60分以内に初回投与を完了することを強く推奨する(グレードA)」とされています。
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
分母:全身麻酔手術で、予防的抗菌薬が実施された手術件数
分子:分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数
【解説】
手術部位感染(SSI: Surgical Site Infection)は、周術期の重大な合併症の一つです。SSIは入院期間の延長、医療費の増加、予後の悪化を引き起こすため、予防的抗菌薬投与(SAP: Surgical Antimicrobial Prophylaxis)による感染予防が非常に重要です。その中でも、「適切なタイミングでの投与」は、最も重要な因子の一つとされています。
○術前1時間以内の投与の科学的根拠
予防的抗菌薬の効果を最大限に発揮させるには、手術開始時に十分な組織内抗菌薬濃度が必要です。抗菌薬の血中・組織移行動態を考慮すると、点滴投与開始から組織移行・定常状態に達するのにおおよそ30〜60分かかるとされます。よって、手術開始の60分以内に投与を完了することが推奨されています。また、日本化学療法学会/日本外科感染症学会「外科領域における抗菌薬適正使用のガイドライン2020」においても「術開始60分以内に初回投与を完了することを強く推奨する(グレードA)」とされています。
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 43077 | 16 | 0.04 |
【定義】
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
分母:退院患者の在院日数の総和(同日入退院、入院時に褥瘡ありの患者は除く)
分子:褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡)の発生患者数
【解説】
褥瘡対策委員会では、リンクスタッフの育成を行っています。委員会メンバーとリンクスタッフとで月2回の回診時にディスカッションを行い、褥瘡の悪化防止や新規発生予防に努めています。
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
分母:退院患者の在院日数の総和(同日入退院、入院時に褥瘡ありの患者は除く)
分子:褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡)の発生患者数
【解説】
褥瘡対策委員会では、リンクスタッフの育成を行っています。委員会メンバーとリンクスタッフとで月2回の回診時にディスカッションを行い、褥瘡の悪化防止や新規発生予防に努めています。
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合ファイルをダウンロード
| 65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 1651 | 1628 | 98.61 |
【定義】
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
分母:65歳以上の退院患者数
分子:分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数
【解説】
65歳以上の患者に栄養スクリーニング、栄養アセスメントを行い、栄養リスク症例を抽出しております。
抽出された栄養リスク症例は栄養サポートチーム(NST)回診の対象となり、ベッドサイドで栄養アセスメントを行い、結果に基づき栄養ケアプランを提示しております。
定期的に再評価を行い、栄養ケアプランを見直し、栄養改善に取り組んでおります。
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
分母:65歳以上の退院患者数
分子:分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数
【解説】
65歳以上の患者に栄養スクリーニング、栄養アセスメントを行い、栄養リスク症例を抽出しております。
抽出された栄養リスク症例は栄養サポートチーム(NST)回診の対象となり、ベッドサイドで栄養アセスメントを行い、結果に基づき栄養ケアプランを提示しております。
定期的に再評価を行い、栄養ケアプランを見直し、栄養改善に取り組んでおります。
身体的拘束の実施率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 44609 | 1692 | 3.79 |
【定義】
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
分母:退院患者の在院日数の総和
分子:分母のうち、身体拘束日数の総和
【解説】
身体拘束は患者の自由を制限し、基本的人権や人間の尊厳を守ることを妨げる行為であることを前提として考え、「身体拘束は原則禁止」という基本方針としています。
当院では、多職種(医師・看護師・薬剤師・作業療法士・医事課事務員・医療安全管理者)による「身体拘束最小化チーム」を発足し活動しています。
身体拘束中の患者のラウンドを実施し、3要件を満たしているか・漫然と身体拘束を継続していないか・解除に向けたカンファレンスが実施出来ているか等を検討し、助言を行っています。
今後もスタッフ1人1人が「身体拘束による弊害」を理解し、低い水準での身体拘束実施率が維持できるように病院全体での取り組みを継続していきます。
対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
分母:退院患者の在院日数の総和
分子:分母のうち、身体拘束日数の総和
【解説】
身体拘束は患者の自由を制限し、基本的人権や人間の尊厳を守ることを妨げる行為であることを前提として考え、「身体拘束は原則禁止」という基本方針としています。
当院では、多職種(医師・看護師・薬剤師・作業療法士・医事課事務員・医療安全管理者)による「身体拘束最小化チーム」を発足し活動しています。
身体拘束中の患者のラウンドを実施し、3要件を満たしているか・漫然と身体拘束を継続していないか・解除に向けたカンファレンスが実施出来ているか等を検討し、助言を行っています。
今後もスタッフ1人1人が「身体拘束による弊害」を理解し、低い水準での身体拘束実施率が維持できるように病院全体での取り組みを継続していきます。
更新履歴
- 2025/9/29
- 2024年度(令和6年度)病院公開指標へ更新
地域連携部
【医療・福祉機関の皆さまへ】
受診相談・転院相談はこちらまで
(受付時間は外来受付時間に準じます)
外来予約センター(再診のみ)
受付:13時30分〜17時(平日のみ)
新患・初診の方は直接お越し下さい
人間ドック・予防接種
受付:13:30〜16:30(平日のみ)
代表窓口
熊本県菊池郡菊陽町原水2921



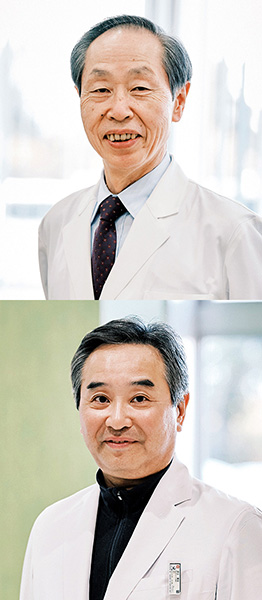







対象患者:医療保険適用患者で一般病棟退院患者(自賠責・労災・自費等の患者、1入院期間中に包括ケア病棟のみの患者は除く)
分母:肺血栓塞栓発症リスクレベルが「中」以上の手術をした患者
分子:分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者
・リスクレベルが「中」以上の手術は、「肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断、治療、予防に関するガイドライン(2017年改訂版)」(日本循環器学会等)に準じて抽出。
【解説】
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」にかかわらず、全身麻酔・腰椎麻酔の手術に対して、フットポンプ・弾性ストッキング等を使用し、肺血栓塞栓症の予防につとめています。